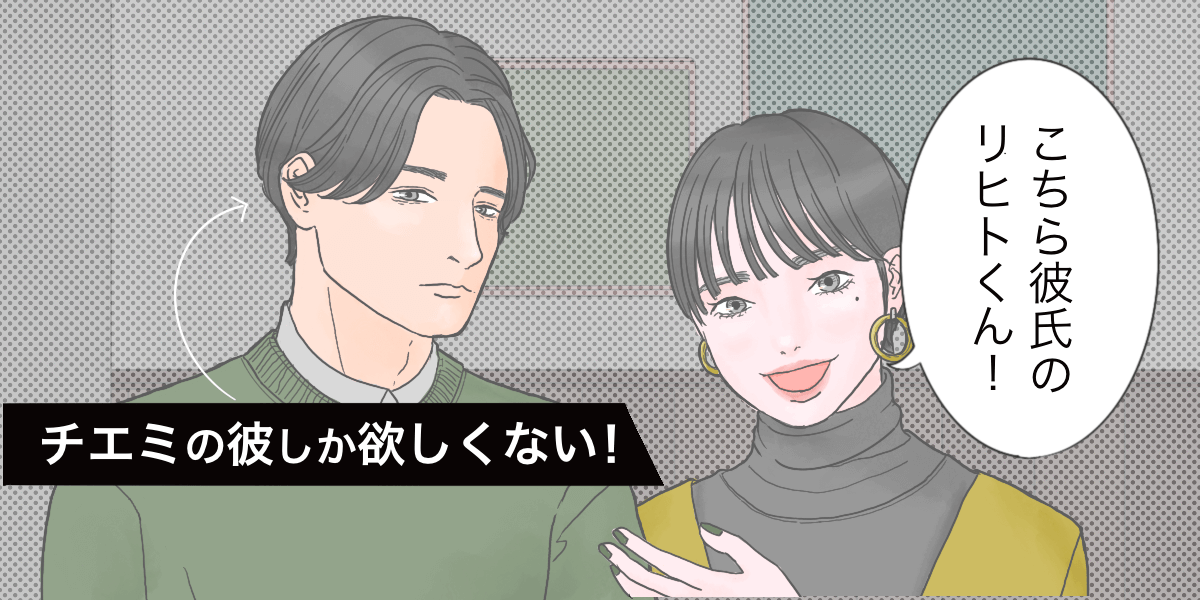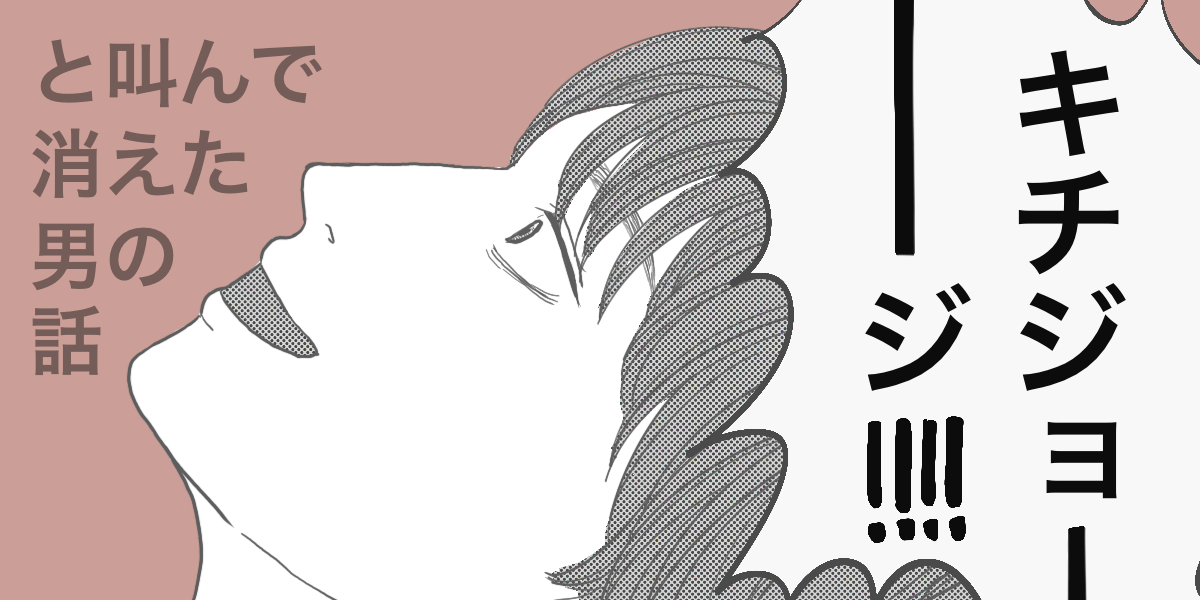高校時代を思い出す時、まず頭に浮かぶのは教室ではなく通学電車だ。通学の30分間で、数えきれないほど痴漢に遭った。ある時は大学生風の男に密着され、ある時は父親よりも年上と思われる数人の男に取り囲まれた。初めて下着に手を入れられた日、教室についた瞬間……いや、正しくは友達の顔を見た途端に涙が止まらなくなった。心配した友人たちはわたしを保健室に連れて行き、放課後には先生を交えた相談の時間を設けてくれた。
「あなた、大人しそうに見えるからねぇ……」
担任だった50代の女性教師は困ったように頬に手を当てた。先生から受けたアドバイスは、時間や車両を頻繁に変えるという、わたしでも思いつくものだった。
「親御さんに付き添ってもらうのはどう?」
母が専業なのを知っていたから出た言葉だと思う。だけどそれこそ絶対に無理だった。娘が毎日痴漢に遭っているなんて知ったら、母はどんなに傷つくか。心配性な母は、毎日のように「困っていることはないか」「何か怖い目にあっていないか」とわたしに尋ねる。日々積み重ねた「大丈夫」を嘘だと告げるのはあまりに酷だ。
「……要するにさ、ナメられてるってことなんじゃん?」
そう言ったのは和美だった。路線は違うが、同じような距離を通学してきているのに、和美はほとんど痴漢に遭っていないと言う。わたしたちの通っていた高校は校則がゆるく、勉強さえ手を抜かなければメイクの類も黙認されていた。当時の和美はほとんど金に近い茶髪で、スカートも短かった。
「こいつは騒ぐぞ、黙ってねぇぞ、ってのを見た目で示せばいいんだよ」
その週の日曜日、和美の家に泊まりに行った。翌朝、和美の手によりメイクを施され、スカートを短く折ったわたしは別人のようだった。「なるべく気が強く見えるように」とアイラインを濃く引いてもらった目元が力強い。猫背になるな、違和感を感じたらすぐ睨め、などと姿勢と態度を指導され、ついでにガムを噛みながら駅に向かう。いつでも発信できる状態にした携帯を握りしめ、わたしは満員電車に乗り込んだ。和美は隣の車両にいて、連絡があればすぐに来てくれるという。けれど、学校の最寄りの駅に着くまで、わたしの指が発信ボタンを押すことはなかった。
「大丈夫だった?」
「うん。……本当に、大丈夫だった」
露出が増えたにも関わらず、被害を受けずに済んだことに驚いた。普段のわたしはパンフレットに載ってもいいくらい、きちんと制服を着ていた。大人が決めた制服を、大人が決めた通りに着ていたのに、制服はわたしを守ってくれなかったのだ。